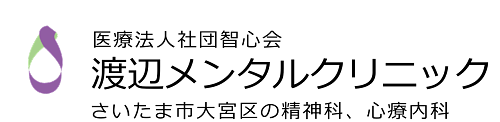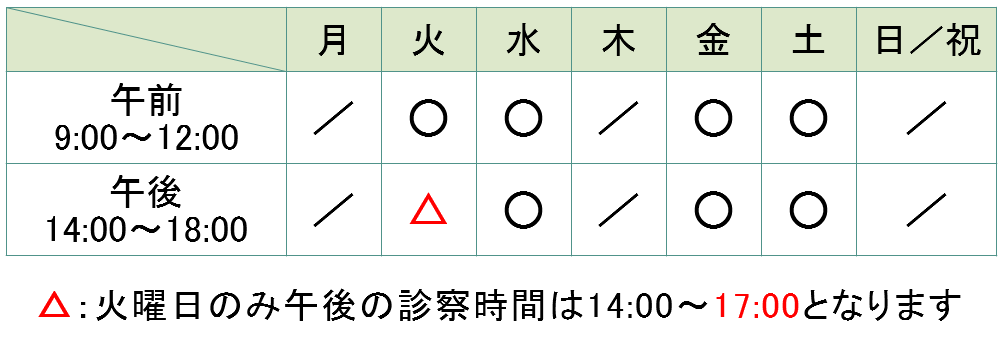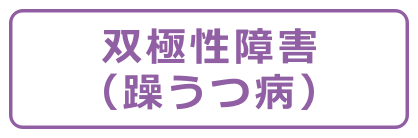









うつ病
うつ病とは
うつ病になる原因はまだはっきりとは分かっていませんが、脳内の神経伝達物質が正常に機能しなくなることで発症すると考えられています。
環境の変化や大切な人との別れなど、辛い経験や悲しい体験によってストレスが蓄積し、「1日中気分が落ち込んでいる」「何をしていても楽しめない」といった状態が続いている場合、うつ病の可能性があります。
うつ状態の人は「自分はダメな人間」で「周りに迷惑をかけている」などと思考がネガティブになります。
もし、うつ病かも?と思ったら、早めの受診をおすすめします。
主な症状
・やる気や意欲が湧かない
・興味や関心がなくなった
・感情を表に出すことが減った
・食欲がない
・眠れない、もしくは寝すぎてしまう
・疲れやすい
・思考力や注意力が低下している
・イライラしやすい
・死にたいと考えるようになる
治 療
まずは十分な休息が必要です。
ストレスを感じる場所へは行かずに心身をゆっくり休めることが大切です。
職場や学校から離れて自宅でゆっくり過ごすことで、早期であれば症状が軽減することもあります。
また、状況に応じて薬物療法を併用することもあります。
すぐには効果は表れないので継続して服薬する必要があり、再発を軽減するために心理療法を用いる場合もあります。
どのような治療をおこなうのか主治医とじっくり話し合い、その方の生活に合わせた適切な組み合わせで治療していきます。
うつ病の治療の基本は「ゆっくり、あせらずに」です。
栄養型うつ
栄養型うつとは
栄養型うつとは、栄養の問題に起因するうつ状態のことです。
うつ状態を引き起こす可能性のある栄養の問題には、たんぱく質やビタミンB群の欠乏・鉄欠乏・亜鉛欠乏などがあり、疲れやすい・気持ちが沈む・やる気が出ない・眠りが浅いなど、精神疾患としてのうつ病の症状と似ています。
うつ病の診断で抗うつ剤を処方されても中々良くならないという方の中には、栄養の問題が隠れていることがあります。
主な症状
・疲れやすい
・眠りが浅い
・気持ちが沈む
・やる気が出ない
・集中力が落ちている
・爪が割れやすい、柔らかい
・髪の毛が細い、抜けやすい
・肌が荒れる、シミやシワが増えた
治 療
精神疾患としての典型的なうつ病と鑑別するために、血液の栄養解析が必須となります。心身の不調時は、食事をしていても栄養状態の悪い人が多いです。
辛い症状をすぐに和らげるための対症療法をしつつ、根本的な体質改善のための原因を探りながら、必要な治療を行っていきます。
原因は個人差があるため、問診と検査を元にご本人と相談しながら精神状態・体力・生活背景を加味し、解決策を決めていきます。

双極性障害(躁うつ病)
双極性障害
双極性障害は、気分が落ち込み憂うつになる「うつ状態」と、気分が高揚し何でもできると活動的になる「躁状態」を繰り返しおこします。
躁状態になると「次々とアイデアが浮かんでくる」「衝動買いをする」などといった行動がみられます。
躁状態の時はハイテンションで気分がよくなっているので、本人には病気の自覚がないことが多く、そのため周りの人が「なんとなくおかしい」「いつもと違う」と違和感を持ち困惑してしまう場合があります。
また、うつ状態の時はうつ病と同様の症状が現れます。
主な症状 – 躁状態 –
・睡眠時間が少なくても元気に活動する
・次々と色々なアイデアが浮かんでくる
・買い物やギャンブルに大金をつかう
・自信に満ち溢れている
・注意散漫になる
・多弁になり話し続ける
・人の意見に耳を貸さない
治 療
薬物治療と心理教育が大切です。
症状が多様なので、お薬の治療を行う際は主治医とよく相談して決めていきます。
最初はうつ病だと思い治療を受けていたのに中々回復せず、実は双極性障害だったというケースもよくあります。
処方されたお薬の用法・用量をよく守り、定期的な血液検査をおこなっていくことが必要です。
また、躁状態の時は自覚がないことが多いので、自分自身の病気を理解しておくために心理教育がより必要になっていきます。
自分の病気の特性を理解し、自らコントロールできるようになることを目指していきます。
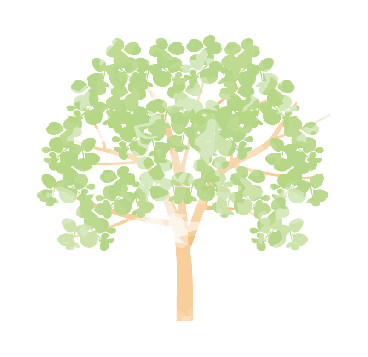
不安障害(パニック障害)
不安障害・パニック障害とは
突然、動悸・めまい・息苦しさ・手足の震え・発汗などの発作が起き、それらが日常生活に支障をきたしている状態をパニック障害といいます。
この発作は「自分はこのまま死んでしまうのではないか?」と思うぐらい強いもので、自分でどうにかしようと思ってもコントロールができません。
そのためパニック発作が起きたら、不安を感じる場所を避けるようになっていきます。
特に、電車・エレベーター・会議室など、自由に行動することを制限されてしまう密閉された空間がその対象になりやすいです。
最初この発作が生じ、その後に予期不安が現れて広場恐怖を考えるようになっていきます。
(予期不安)
「また発作が起きるのでは?」「今度こそ死んでしまうのでは?」などといった不安をもつようになります。
(広場恐怖)
発作がおきたときに「すぐにそこから逃れられないのではないか?」という密閉された場所や自由に身動きがとれなくなる状況で、そのような場所・状況を避けるような行動をとるようになります。
治 療
まずは内科的な疾患でないか検査の上、異常がなければ薬物治療と精神・心理療法をおこなっていきます。
お薬は抗うつ剤(SSRI)や抗不安薬がメインになります。
その際、薬の副作用や依存性に充分配慮することが大切になりますので、処方している薬が合っているか等、お話をしっかりと聞きながら治療をおこなっていきます。
また、暴露療法などの行動療法や認知行動療法の効果があると言われていますが、その方に合ったカウンセリングを提供していきますので、医師や臨床心理士・公認心理師に相談しながらすすめていきます。

強迫性障害
強迫性障害とは
強迫性障害は不安障害の一種です。
例えば「手に菌がついているのでは?」と何時間も手を洗い続けたり「戸締りや火の元をしっかり確認したか?」と何度も繰り返し見に戻ったりする行為を強迫行為といい、自分の意思に反して何度も頭に浮かんできて払いきれない考えを強迫観念といいます。
強迫行為・観念は本人にとっては苦痛で、不安を解消するために「しなければならないこと」となっています。
主な強迫行為・観念
(不潔恐怖)
汚れや細菌などが気になって、過剰に手洗い・入浴・洗濯を繰り返す
(確認行為)
戸締りや火の元のスイッチなど閉め忘れていないか過剰に確認する
(加害恐怖)
誰かに危害を加えたかもしれないと不安になり、それが頭から離れずニュースや通った道を確認せずにいられない
(儀式行為)
自分で決めた手順ですすめないと恐ろしいことが起きると不安になり、同じやり方を繰り返す
治 療
薬物療法(抗うつ薬)と認知行動療法が効果的と言われています。
投薬は最初は少量からはじめ、薬との相性を確かめながら増量していき、副作用など主治医に相談しながら治療をすすめていきます。
それと並行して、不安になると出てくる行動や観念を無理のない範囲で我慢し、成功体験を重ねていきます。
医師や心理士とじっくり話し合いながら、頑張っていきましょう。

PTSD:Post Traumatic Stress Disorder – 心的外傷後ストレス障害 –
PTSDとは
命の危険に直面するなどの強い恐怖体験をした後、その記憶が自分の意志とは関係なく再生されたり夢を見たりして、不安や緊張が高まり現実感がなくなる症状が1か月以上続いている状態をPTSDといいます。
その体験の記憶は統合されていないので、関連したある一部分の記憶が蘇ると、それが色々な断片化した記憶にはたらきかけ、なにもかもが恐怖に感じられます。
このような状態から自分を守るために、一部の記憶を想起できなくさせたりします。
症 状
・ふとしたときに辛い記憶が蘇る
・緊張状態が続いている
・常にイライラする
・よく眠れない
・辛い場面を想起するような場所を避ける
・感情や感覚が麻痺する
治 療
抗うつ薬(SSRIなど)が有効とされていますが、心理療法による治療が最も効果的とされています。
トラウマを扱う認知行動療法(持続エクスポージャー法、EMDRなど)が代表的です。
まずは主治医の先生によく話を聞いてもらい、薬物療法と並行して臨床心理士・公認心理師による心理療法をおこなっていくこととなります。

発達障害
発達障害とは
生まれつきもった特性で、自閉スペクトラム症・注意欠如多動症(ADHD)・学習障害・知的障害などが含まれます。
最近では「大人の発達障害」といわれる方が増えてきています。
大人の発達障害の方は、家庭や職場で周りの人と比べてミスが多かったり作業が遅かったりして、自分で直そうと思ってもうまくいかず、他者から叱責を受け自信を失い、うつ病や適応障害などを発症していきます。
つまり、発達障害が根底にあり、その結果「二次的にその他の疾患が発症している」という場合が多くみられます。
(自閉スペクトラム症)
・相手の意図が理解できない
・文字どおりに言葉を受け取ってしまう
・冗談や皮肉がわからない
・集団行動が苦手
・自分の考えや意図を相手に伝えることが難しい
・興味や関心の幅が狭い
・悪意がなく言ったことなのに相手がよく怒っている
・ルールなどやり方がきまっているとやりやすい(仕事では独自のルールがある)
・感覚過敏(音・光・においなど)
(ADHD)
・集中力が続かない
・気が散りやすい
・忘れっぽい
・優先順位がつけられない
・整理整頓ができない
・遅刻が多い
・じっとしていないといけない場面でそれができない
・衝動買いをする
・思いついたら即座の発言や行動がある
治 療
まずは心理検査を受けていただき、色々な側面から発達障害かそうでないかをみていきます。
自閉スペクトラム症の方は、自分が何を得意とし何を苦手としているのかを理解していきます。
苦手としていることについては、集団の中で社会的スキルを学ぶ練習をし、カウンセリングを通して少しずつ困りごとを解決していきます。
ADHDの方は薬物療法も効果的とされています。
それと並行して、自分が苦手なことに対してどう工夫してどう対処していくかを身につけていきます。
大切なことは職場や家庭の方の障害への理解であり、周囲の協力に支えられる環境が必要となります。
また、日常生活の中で自分の気持ちを相手にうまく伝え、自分で対処していける力を身につけていくことを目的とした【SSTクラブ】を開催しております。

統合失調症
統合失調症とは
考えや気持ちがまとまらなくなる疾患で、脳の働きを統合することが難しくなっているため発症します。
症状には陽性症状と陰性症状があります。
また、約100人に1人の割合で発症するといわれています。
早期発見・早期治療が回復を早めますので、気づいたら早めの受診をおすすめします。
症 状
【陽性症状】は妄想や幻覚が主となります。
誰もいないのに命令する声や悪口が聞こえたり、「誰かにずっと監視されている」「あるはずのないものがそこに見えている」などの症状が表れます。
【陰性症状】は「喜怒哀楽が乏しくなる」「自分の世界に閉じこもり、他者と交流しなくなる」「意欲がなくなる」などの症状が表れます。
また、周囲からみると話がまとまっておらず、支離滅裂なことや独り言をブツブツと言っていたり、いつも不安そうで緊張していることが多くなったと感じます。
治 療
薬物療法とリハビリテーションが主な治療になります。
再発の防止や社会生活機能の維持を目指します。
再発を繰り返すことが多い疾患なので、安定してきたからといって勝手な判断で薬を飲まなかったり減らしたりすることは重症化する危険があります。
しっかりと主治医の先生と相談して治療していきましょう。

適応障害
適応障害とは
ある特定の状況や出来事がストレスとなり、感情や行動に症状が現れて日常生活(仕事、家事育児、学業など)に支障をきたす疾患です。
ここでいう「ストレス」とは重大な生活の変化(進学・就職・異動・昇進・結婚・出産など)のことを指します。
ストレスの原因が特定されているので、一旦そこから距離を置くと症状は次第に改善しますので、早めの受診が肝心です。
症 状
症状は人によって異なりますが「何をしていても楽しくなくなる」「イライラしやすくなる」といった不安感・焦燥感・緊張感などの感情面にあらわれる症状を訴える方が多く、行動面では暴飲暴食・無断欠勤・けんか・無謀な運転などの攻撃的な側面がみられます。
治 療
まずはストレスとなっている状況や出来事から離れ、休養をしっかりとって環境調整をしていくことが必要になります。
しかし環境調整がうまくいかなかったり、環境調整をしても中々症状が改善しない場合は、薬物治療やカウンセリングをおこなっていきます。
カウンセリングでは、その人がストレスと感じる状況に対して行動や意識を変え、適応力を高める方法を一緒に考えていきます。
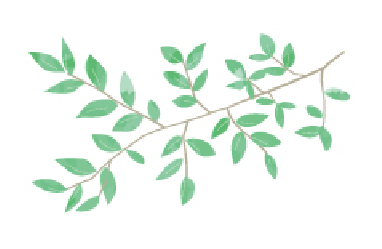
起立性調節障害(OD)Orthostatic Dysregulation
※診断については専門の科を受診してください
起立性調節障害とは
起立性調節障害は、朝起きられない・立ち上がるとクラっとする・失神・動悸・頭痛などの症状を伴う、自律神経機能不全の一つです。自律神経による循環の調節が障害され、脳への血流が低下することに起因します。
朝起きられないことで日常生活が著しく損なわれ、不登校や引きこもり・会社に行けないなど、社会生活をおくる上で大きな支障となります。
主な症状
・朝起きにくい、立ちくらみ、失神
・動悸、息切れ
・吐き気、腹痛、頭痛
・倦怠感、体が重い、疲れやすい、集中力が続かない
・午前中調子が悪く、午後から夜にかけて元気
・イライラしやすい
治 療
まずは食事や睡眠など生活リズムを整えることが大切です。
背景にストレスがある場合は、環境調整をしたりカウンセリングを利用し対応力を身につけたりすることも有効です。
また栄養不足により、食事を摂っていても自律神経の乱れが生じるため、採血での数値の確認は必須となります。
薬物療法の中でも漢方薬は、個々の体質と症状に応じて調整できるため、良いサポートとなります。

PMS(月経前症候群)/PMDD(月経前気分不快障害)
※まずは婦人科を受診して頂いたうえで、ホルモン値を含む採血データや処方薬を踏まえて診察を勧めていきます。
PMS・PMDDとは
原因ははっきりとはわかっていませんが、女性ホルモンの変動が関わっていると考えられています。排卵のリズムがある女性の場合、排卵から月経までの期間の後半に卵胞ホルモンと黄体ホルモンが急激に低下し、脳内のホルモンや神経伝達物質の異常を引き起こすことがPMSの原因と考えられています。しかし脳内のホルモンや神経伝達物質はストレスなどの影響も受けるため、PMSは女性ホルモンの低下だけが原因ではなく、多くの要因から生じると言われています。その中でも特に精神症状が強いものがPMDDです。
主な症状
| 〇PMS | |
| <体の不調> ・肌荒れ ・倦怠感 ・胸が張る ・むくみ ・食欲不振 | <こころの不調> ・イライラ ・何でもないことで泣いてしまう ・怒りっぽい ・日中の眠気 ・ボーっとする |
| 〇PMDD | |
| ・抑うつ気分 ・絶望感 ・不安、緊張、怒り ・情緒不安定 ・対人関係上のトラブルの増加 ・趣味の減退 ・集中力低下 |
治 療
婦人科では主に経口避妊薬や選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)などが用いられることがありますが、ビタミンD・ビタミンB群・マグネシウム・亜鉛・鉄といった各栄養素が不足することにより症状が悪化する可能性があります。
当院でも採血をしますが各栄養素のデータにしっかりと目を通し、ご本人様と相談しながら漢方薬・鎮痛剤・向精神薬といったお薬を考慮していきます。

更年期障害
更年期障害とは
更年期障害は月経不順に加えて、心身にさまざまな症状が表れます。それは女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少することで、ホルモンのバランスが崩れるからです。
主な症状
・気分の落ち込み
・イライラ
・情緒不安定
・意欲低下
・不眠
・訳もなく涙が出る
・好きなことでもやる気になれない
治 療
症状の出方は人により様々で、治療はホルモン補充療法が主体となりますが、うつ症状や不眠・イライラが強い場合は抗うつ薬・抗不安薬・気分調整薬などが考慮されます。
当院では問診や血液(主に栄養素の部分)を元にホルモンバランスや自律神経の乱れを調整することを目指し、個々の体質に応じた漢方治療と栄養療法を併用します。
また必要に応じてカウンセリングを行うことで症状緩和をサポートします。